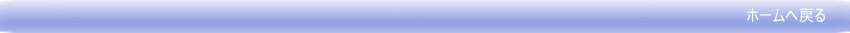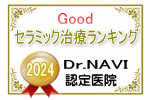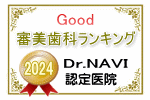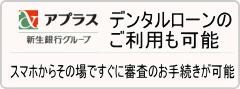抜歯の質問
抜歯・親知らずについて
抜歯・親知らずのよくある質問集です。
わからないことがあれば、ご参考になさってください。
- 歯を抜けたままにするとどうなる?治療方法?
歯を失ってしまった後、まだ、お食事に支障がないからといって、そのままにしてしまうと、残された歯に加わる負担が大きくなるため、それらの歯の寿命が短くなります。それだけでなく、隣の歯が抜けた部分に倒れてきたり、噛み合わせの相手を失くした歯が伸びてきたりして、歯並びや噛み合わせが狂ってしまいます。噛み合わせが狂うと、左右の顎の関節がバランスを失い、顎関節症という病気を起こすこともあります。顎関節症は、お口を開け閉めする度にポキポキ音が鳴ったり、口が開かなくなったり、頭痛や耳鳴りを起こしたりします。ですから、必ず治療を行って、左右のどちらでもバランス良く噛めるようにすることが大切です。
歯の抜けたところに行う治療には、隣接歯を土台にして被せものでつなぐ固定式の“ブリッジ”や、歯が無い部分の歯茎の上にのせる、取り外し式の入れ歯があります。他に保険は適応されませんが、インプラントという人工の歯根を顎骨の中に植え込む外科的な治療もあります。また、歯が無くなったところに、親知らずなどの歯を移植できる場合もあります。
- 歯を抜いた後の治療の方法はどんなの?
【ブリッジ】
抜けた歯の隣接歯を支えにし、欠損歯を含めて連結させた冠をその支えとなる歯に被せて橋渡をし、噛めるようにする治療法です。治療の流れ
・治療計画
・支台となる歯の形を整える
・噛み合わせの記録
・歯の型取り(印象)
・模型を作製しブリッジの作製
・ブリッジ完成
・適合、噛み合わせ等の調整
・接着剤で装着
以上を2~5回前後の通院で行います。(※根の治療の回数は含みません。)利点
●接着剤(セメント)で歯に固定してしまうので、食事中ずれたりしません。
●被せものの種類を好みに合わせていろいろ選択できます。(白い歯・保険のもの等)
欠点
●虫歯の有無に関わらず、支えになる歯を削る必要があります。
●抜けた歯の本数や場所によっては、保険が効かないこともあります。
●抜けた歯の本数や場所によってはできない場合もあります。
●連続した冠でできているので適切なお手入れが必要です。(歯間ブラシ等)【入れ歯(義歯)】
通常、入れ歯と呼ばれているのは、取り外し式の義歯です。
入れ歯(義歯)は、人工歯と呼ばれる歯の部分、床(しょう)と呼ばれるピンクの樹脂の部分、クラスプと呼ばれる歯に掛ける鈎の部分からできています。ただし総入れ歯(総義歯)にはこの鈎がありません。治療の流れ
・治療計画
・入れ歯を支える歯(鈎の掛る歯)の前処理
・入れ歯の型取り(印象)
・噛み合わせの記録
・噛み合わせや歯並びの確認(試適)
・入れ歯の完成
・適合、噛み合わせ等の調整
・使ってみた後、微調整(調整が何度か必要)
以上を約4回前後の通院で行います。利点
●抜けた歯の本数や場所に関わらず、保険治療が可能です。
●他の歯を削る必要が少なく済みます。
●装着後の調節が比較的可能です。
欠点
●顎の骨がやせている方は、入れ歯ができてからの調整に時間がかかります。
●接着剤で固定しないので、食事中に歯肉との間にものが入り込むことがあります。
●安定が悪く口や舌を動かすとガタつくことがあります。
●床と呼ばれるところが歯ぐきを広く覆うので、違和感が多く感じます。(話をしにくい、食べ物がおいしくない。)
●鈎を掛けている歯に、過重な負担がかかり、歯がグラついてくることがあります。
●食後や寝る前のお手入れが必要です。(毎食後、入れ歯を外して歯と入れ歯の両方を磨き、夜は外して乾燥しないように保管して下さい。)【インプラント(人工歯根)】
歯が抜けた後の顎の骨に、チタンなどでできた人工歯根を植込み、その上に人工歯装着して噛めるようにする治療法です。
固定式で、周りの歯を傷つけることもなく、自分の歯と同じような感覚で噛む事ができます。【歯の移植】
歯が抜けたところに、親知らずなどの噛むのに使っていない歯を移植して噛めるようにする治療法です。
傷口が大きい割に痛みも少なく、ご自分の歯を利用するため拒絶反応もなく安全です。条件が揃えば保険治療が可能です。
- 抜歯後の注意って何?
出血があるときは、滅菌済みのガーゼをきつめに噛んで圧迫してください。唾液に少し血が混じっている程度でしたら心配入りません。
出血が止まりにくい時は、血を受けるタオルを頭の下に置き、枕を少し高めにして横になり安静にしてください。
麻酔が2時間程度効いておりますので、誤って舌や頬を噛まないように注意してください。また熱いもののやけどにも注意してください。できましたら、麻酔が切れてからお食事等をするようにしてください。
麻酔が切れて痛みが我慢できないときは、痛み止めをお飲み下さい。
口腔内を清潔に保ち、歯ブラシ等を傷口に触れないようにしてください。
当日は、強く口をゆすいだりすると傷口から再び出血してしまうことがありますので、軽くゆすぐ程度にしてください。当日は、激しい運動や長風呂、お酒等は控え、なるべく安静を保つようにしてください。
- “歯を抜く”と言うことについての、予備知識?
歯科医院に通院していて、「残念ですが、この歯は抜かなければなりません」という言葉を聞くと誰しも一瞬ドキッとするものです。
歯を抜くにあたっての予備知識として解説します。
麻酔の方法は、全身麻酔と局所麻酔の2つに大きく分けることができます。
通常、歯を抜く場合は、局所麻酔(治療する範囲のみを部分的に麻酔する方法)の中の浸潤麻酔という方法で行います。
このとき用いる麻酔薬は劇薬の指定を受けていますが、使用量が1ml~5mlと少量なことと、メーカーからアレルギーの少ないものが開発されていますのでほとんどの場合心配いりません。ただし、アレルギー体質の方は注意が必要です。
また、体内に入った麻酔薬は、血清や肝臓中で速やかに分解され尿と共に排泄されます。ですので、妊婦の方にとっても、麻酔薬が胎盤を通過することはなく安全です。
一方、麻酔をするときに用いる注射の針のサイズは、歯科のものは医科のものより細く出来ていますので、刺したときの痛みも軽減されています。それでも注射が恐いという方は、針を刺す前に予めその部分をしびれさせるために、表面麻酔を塗る方法があります。麻酔の前の予備知識
・麻酔は唇の近くにすると唇がしびれ、鼻の近くは鼻が詰まった感じがしたりします。
・麻酔薬の中には、使用量が僅かでも効果が長持ちするように、“血管収縮剤”というものが入っています。その薬の影響で、麻酔の後、心臓の鼓動は激しくなり、一時的に血圧が上昇します。
高血圧の方や、以前に麻酔を打って気分が悪くなったり、アレルギーの出た方は、予めお申し出下さい。
心臓に疾患があったり、喘息、アレルギー体質の方も予めお申し出下さい。
麻酔の後、気分が悪くなったり(宙に浮いた感じになったり)、頭痛が生じたときは、その旨を医師に伝えてください。
・治療前に緊張している場合は、別のこと(楽しいことやおもしろいことなど)を考えたり、足上げ腹筋をしたりして、気を紛らわして下さい。呼吸は深くゆっくりしてください。レントゲンを撮って予め抜く歯の状態を調べたりしますが、平面で見る写真と実際は異なっていることが多く、歯と骨や歯茎が癒着していることもあり、意外と抜くのが大変なことがあります。
特に、複数の歯の根がそれぞれ足を広げている場合や、歯根が曲がっている場合、斜めに生えている場合などは、抜くのに時間がかかります。
- 抜かなければならない歯ってどんな場合?
・C4(進行した虫歯)
C4とは、虫歯により歯のほとんどが無くなってしまい、歯の根まで虫歯に犯されてしまったものを言います。
歯根部分がある程度残っていて炎症が少ない場合は、治療をして被せものなどを入れることができることもありますが、歯根がほとんど残っていない場合や腫れや炎症がひどい場合は、残念ながら抜いてしまうしかありません。・P4(進行した歯槽膿漏)
P4とは、歯周病によって歯を支えている骨がほとんど無く、歯の動揺が大きく上下にも動いてしまうような状態です。歯の根の周りの炎症は強く、歯が浮いているため噛むと痛みがあり、腫れがある場合もあります。そのままにしていてもいずれ自然に抜けてしまいますが、噛み合わせや治療等に支障がある場合は抜かなければなりません。・歯根が割れてしまった
割れ方にもよるのですが、根っこが割れてしまった場合は、恐らく噛むたびに痛みが走ります。一部分が欠け、欠けた部分を切除して治療をすることができる場合もありますが、根っこが縦に割れてしまった場合は、残念ですが虫歯になっていなくても、ほとんどの場合抜くことになります。・歯根の先に、大きな病巣のある歯
通常、歯根の先に病巣がある場合、根の中をきれいに消毒してから被せものなどをしますが、病巣が大きくなりすぎて広範囲に広がっている場合は、消毒や外科的な治療でも治せなくなります。この場合は、残念ですが抜くことになります。歯根の先に病巣は症状がでにくいため、発見が遅れることがあり、痛みや腫れが出たころにはかなり進行している場合がありますので、定期的な健診が大切です。・親知らずの辺りが痛い・腫れた
親知らずは、顎の骨格の成長が終わった大人になってから生えてくるため、倒れて生えていたり、周りの歯茎が被っていたりすることが多く、腫れや炎症が起きやすい場所です。また、生える過程で手前の歯を押したり、間にものが溜まりやすいため虫歯になりやすくなります。歯茎や他の歯へ悪影響のある生え方や状態の親知らずは、抜いたほうがよい場合もあります。・矯正治療の必要性から
歯並びをきれいにするためとは言え、虫歯ではないきれいな歯を抜くことには、ためらいを感じるものです。しかし、その歯がある限り歯並びは乱れ、ほかの歯を虫歯の危険にさらしてしまう場合もあるので、残念ですが抜くことになります。
- 親知らずって抜かなきゃいけないの?
親知らずというだけあって、親の管理を離れた大人になってから、お口の一番奥に生えてきます。そのため、生えてくるころには顎骨の成長は終わっており、頭を出すスペースがない場合は、半部しか顔を出さなかったり、横に向かって生えてきたり、骨の中に埋まったまま出てこないこともあります。
半分しか顔を出さないものや横に生えている親知らずは、歯のエナメル質部分に歯茎が被っています。エナメル質は歯茎とくっつかないため、そこに隙間(ポケット)ができものが溜まりやすくなります。一番奥で歯ブラシが届きにくいこともあり、虫歯や歯肉の炎症がおきやすくなります。
特に横に向いて生えてくる親知らずは、手前の歯との隙間にものが詰まりやすく、手前の歯の虫歯の原因になることもあり、成長とともに押されて噛み合せの異常が生じることもあります。
このように様々な症状を引き起こす親知らずは、抜いたほうがよいのですが、状態によってはかなりの難抜歯となるケースが多くあります。
レントゲンで生えている状態を確認し、抜く時のリスクなどをしっかりと医師にご相談ください。
- 親知らずってどうして腫れるの?
性質上、歯の表面のエナメル質と歯茎はくっ付きません。歯と歯茎の隙間に食べかすや細菌が入り込み、寝不足や過労、風邪などによって体力が低下した時などに腫れることが多いです。
☆よくある質問(TOP)に戻る